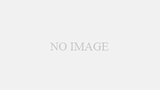娘はHSCでとても言葉に敏感です。そして記憶力もいいので深い意味はない言葉でも娘の記憶に深く刺さってしまう事があります。さらに言われたことをきちんと守りたくて正しくしなくてはいけないという性格で、出来ない自分を責める傾向にあります。小さな頃から私はそんな娘への声掛けに慎重にならざるをえなくて、自分の発言が娘に与える責任が重く娘とのコミュニケーションが苦しく感じる事もありました。
だからなのかはわかりませんが「だってお母さんが言ったから」「お母さんのせいで」そう思われたくなくて、私も間違える事はあるしそんな私の言葉は絶対ではないので、自然となんでも本人に決めてもらうようになっていきました。
何を着るか、何を履くか、何を持っていくかなどの些細なことはもちろん、学校の日に何時に起きて朝に何をするか、宿題をいつやるか、習い事も全部自分で決めるようになっていました。
朝起きてだらだら過ごしていても早くしなさいといいません。遅刻をする日もありますがそれも口を出しません。ただ遅れるなら学校に連絡を入れないといけないよと伝えています。そして案外遅刻しません。朝にだらだら過ごしてギリギリになっても、自分で時計をみながら調整しています。「今日は早めに行こう」とか「今日はギリギリまで家でゆっくりいたい」などその日によって自分で考えて決めているようです。
学校休むかどうかも自分で決めています。熱がなくても、本人が休みたいと言った日は休ませます。
遡ると幼児期から本人に決めさせるという事を意識して過ごしてきたと思います。最初はどっちにする?とか小さな事から、この中からどれか選んでね、など少しずつ範囲を広げていきました。
「今日はたくさん雨が降ってるよ。長靴履く?いつもの靴にする?」というように気温や気候の変化を伝えたうえでどっちにする?どうしたい?と決めてもらったり。
「勝手にさせる」のではなく、
一緒に考える。否定をしない。
失敗をした時には「だから言ったでしょ」と責めずに、「じゃあこうしてみよう」とか「大丈夫」といつでも味方でいてあげる事を意識するようにしました。
こんなに暑いのに長袖着るの?とか、こんなに雨降ってるのに長靴履かないの?という事もあったし、「半袖の方がいいんじゃない?」「長靴の方がいいんじゃない?」というように大人の経験値で先読みをして意見してしまう事は多々あります。それでも最後は本人がこっちでいいと決めたならそれを受け止めて、半袖の着替えを持たせたり、濡れたら履き替えるといいよと靴下の替えを持っていくことを提案したりと、否定するのではなくフォローする方法を話し合う、意見を押し付けずにコミュニケーションを取りながら一緒に決めていくイメージでやっていくうちに段々と本人がきちんとTPOを意識して考え決定出来るようになってきたなと感じています。
「○○しなさい」を言わないようにし「自分で決めていいよ」と声を掛けるようにいつも心がけています。本人にしかわからない理由がきっとそこにあるから。
下の子はまた感じ方が違うようなのでこれからどう成長するかわかりません。同じ親から生まれても性格が違って私が同じ言葉をかけてもそれぞれ違った受け止め方をするのだなと、とても面白いです。
やっぱり育児には正解なんてくて、こう声をかければうまくいくなんてありえない。子供達それぞれに合った寄り添い方を模索していくしかないんですよね。
だけどそれぞれ違った個性をもっている姉弟ですが上に書いた「一緒に考える、否定しない、いつでも味方でいてあげる」これはどんな場面でもどんな子に対しても共通しているんじゃないかなと思います。
お母さんに決めてもらいたい子がいたとすれば、自分で決めなさいと強制せずに子供が望むようにお母さんが決めてあげればいいのだと思います。そして「こっちとこっちどっちが好き?」とちいさな決定をさせてあげて「それいいね」と共感する、そんな小さな積み重ねで自分で決める喜びや自信をつけていってあげたいなと思っています。
ある時、娘がなんでも自分で決めているという話を知人にしたとき「娘ちゃんの事を信じてるんだね」と言われました。
口を出さずに本人に決めさせることと信じる事が繋がっていると考えたことがなかったのですが、そう言われて初めて確かにそうかもしれないと気付きました。学校を遅刻したり休んだり習い事に関しても本人に決めさせることが出来ているのは私が娘を信じているから。ずるで休んだり遅刻したりする子ではないし、困ったことがあれば隠したりせずにちゃんと話してくれる、そうやって娘が信じさせてくれているからだと。
それに気付いたとき、私も同様に娘に信じてもらえる母親でいなくてはいけないなと心に誓いました。それはやっぱり「一緒に考える、否定しない、味方でいる」これを守る事なのだと。私がそんな母親でいる事が親子の信頼関係に繋がり、間違えてはいけない、失敗したくないという気持ちの強い娘が怖がらずに自分で決めていく力になるのだとそう思います。